学齢期の食事のポイント
学齢期の食事のポイント
学齢期(学童期・思春期)の特徴
6歳から11歳頃の学童期は、全身の骨格の成長がみられ、歯も乳歯から永久歯へと生え変わる時期です。運動量が増え、消化・吸収能力や代謝が高まり、食欲旺盛になります。
また、小学校高学年~中高生にかけての思春期は、心と体の発達が著しく、エネルギーや栄養素の必要量が増加します。体組織をつくるたんぱく質はこの時期が最も多く必要になります。また、カルシウムや鉄、ビタミン類などもしっかり摂ることが必要です。
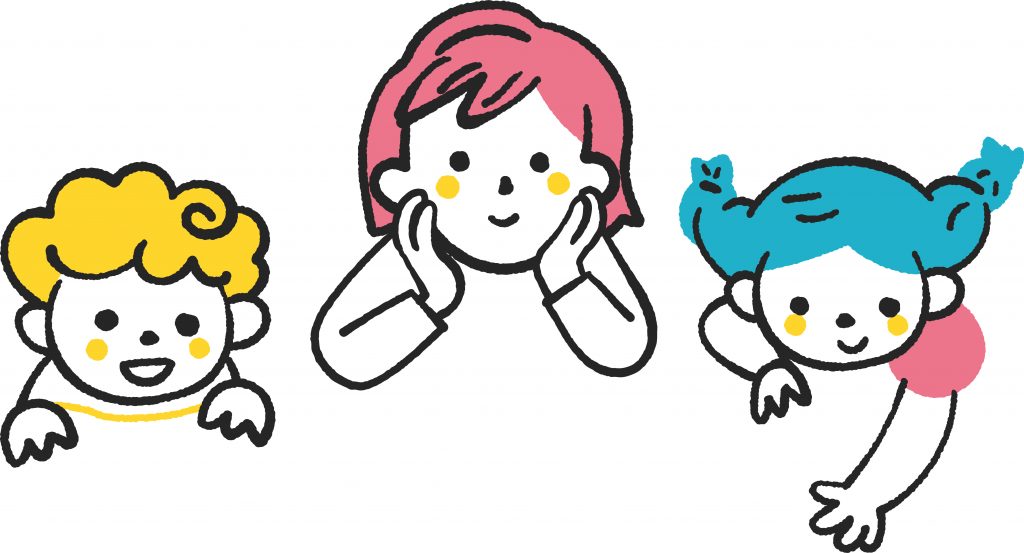
学齢期の食事のポイント
▶良い生活習慣をもとう
▶食事をバランスよく食べよう
▶エネルギー不足に注意しよう
▶地域と食べ物の関わりに関心をもとう
良い生活習慣をもとう
体と心の成長に欠かせないのが、良い生活習慣です。
生活リズムが整っていないと健康と成長に大きな影響が出てしまいます。
良い生活習慣の実践のためには、「食事」「運動」「休息」「睡眠」のリズムが大切です。
朝ごはんを食べよう!
朝食を食べると、眠っていた脳やからだが目覚めます。朝食を欠食すると脳を働かせるエネルギーが不足し、勉強に身が入らない、体がだるい、集中力がないなどの症状が現れます。1日を元気に過ごすためにも朝ごはんを食べる習慣を大切にしましょう。
<朝ごはんが食べたくなるポイント>
「早寝早起きの習慣をつける」「決まった時間に食卓につく」「少しでも食べる習慣をつける」「夜食はひかえる」
おすすめは「朝のお手伝い」です。
植木の水やり、食器並べ・・・など習慣にしては?起きてすぐは食べられないことも多いので、お手伝いで身体を動かすと体が目覚めてきます!
食事をバランスよく食べよう
体が大きく成長する学齢期は、栄養のバランスのとれた食事をすることが大切です。そのためには、いろいろな種類の食品を食べるようにしましょう。
学齢期は、骨量の加齢的変化からみても、体の発育発達の時期であると同時に、骨格の成長が完了し、最大骨量に到達するまでの重要な時期です。骨の形成には、カルシウムの摂取が重要ですが、その他にもカルシウムの吸収を促進するビタミンD、骨へのカルシウムの取り込みを助けるビタミンKの摂取も重要です。エネルギーと栄養素を過不足なく摂取しましょう。
骨の成長に必要な栄養素
| カリウム | <多く含まれる食品> 乳製品、小魚、小松菜、豆腐など |
| ビタミンD | <多く含まれる食品> きのこ類、卵、鮭など |
| ビタミンK | <多く含まれる食品> チーズ、納豆、ブロッコリーなど |
| 摂り過ぎ注意! |
・食塩(ナトリウム) 摂りすぎるとカルシウムの排せつを促します。薄味を心がけましょう! ・リン 摂り過ぎるとカルシムの吸収を悪くします。 リンを多く含む加工食品やインスタント食品の摂りすぎに注意しましょう。 |
エネルギー不足に注意しよう
エネルギーは、体や心を動かすために必要です。 エネルギーを作るためには、炭水化物と脂質、ビタミンが必要です。炭水化物と脂質 がエネルギー源として利用されるときにビタミンが利用されます。また、炭水化物が不足している時には、たんぱく質もエネルギー源として使われます。これにより、体の筋肉量が減って、体が疲れやすくなったりします。
また、体内のエネルギーは、他から借りることができず、エネルギーが不足しているときは節約するしかありません。 このため、エネルギーが不足すると、体のいろいろな所に影響を及ぼしますので、1日3食しっかり食事を摂るようにしましょう。
エネルギー不足による体への影響
・発育期においては、成長や発育に影響がでます。
・女性は、月経になっ たり、初経の時期が 遅れたりします。
・体重が減少し、代謝が落ちたり、貧血になったり、骨密度が低下したり、ホルモンの分泌が 乱れたりします。
女性のやせについて詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。
地域と食べ物の関わりに関心をもとう
京都には、平安京以来千二百有余年の歴史と伝統、海から離れた内陸の盆地という環境の中で育まれた、京都ならではの食文化が形作られています。
京都の食文化について、こちらをクリックして調べてみましょう。